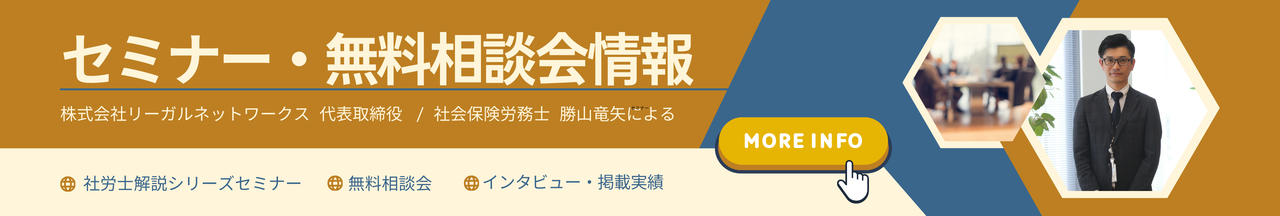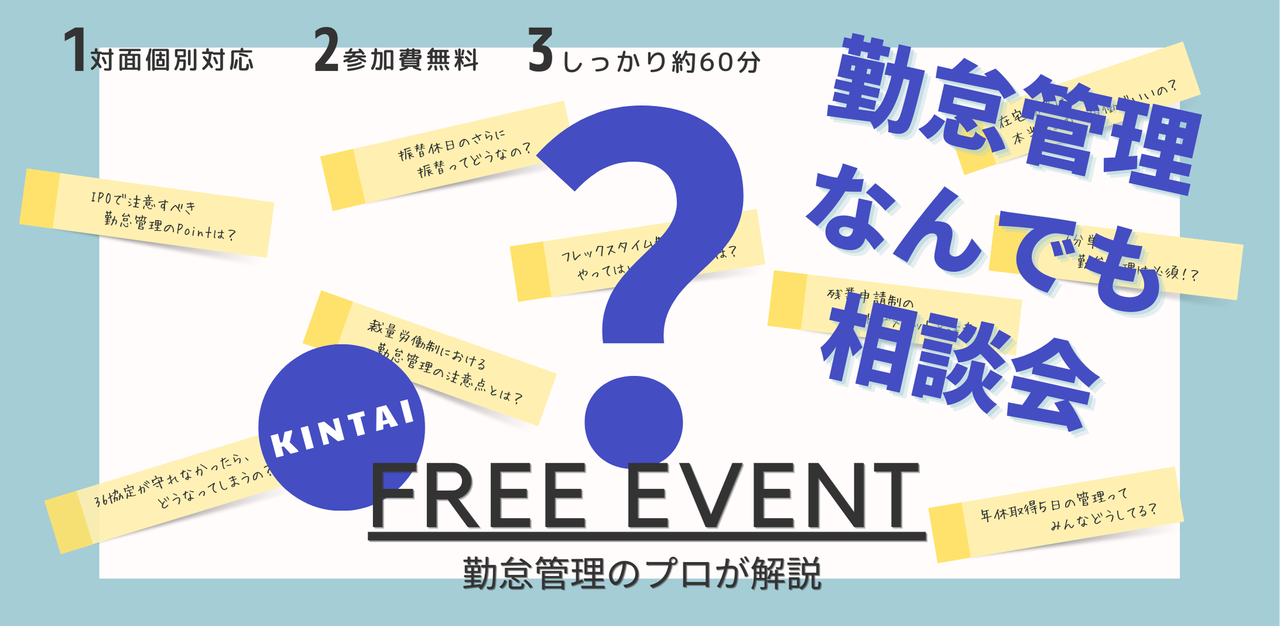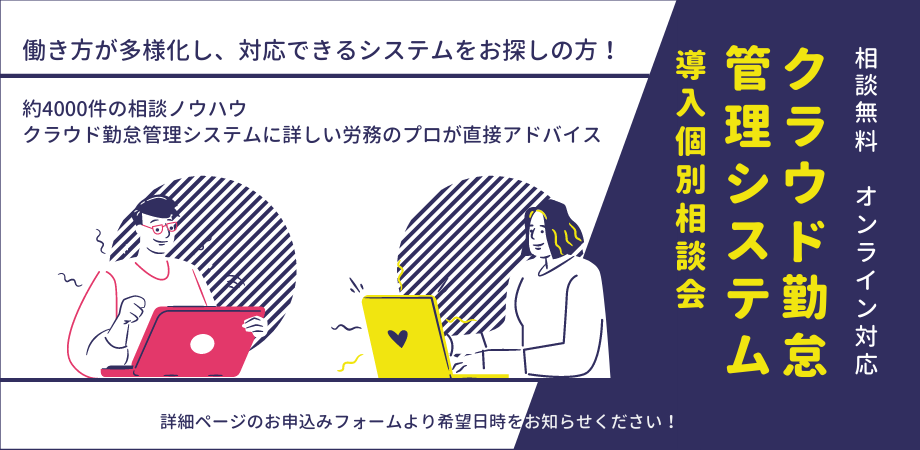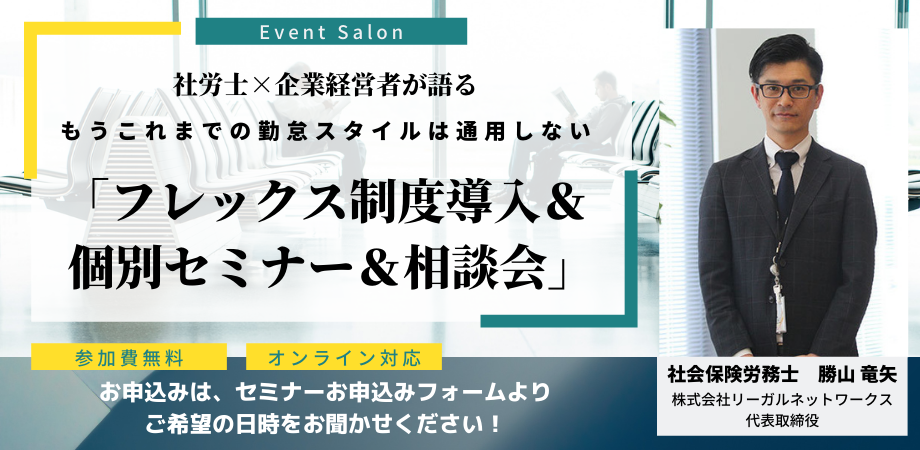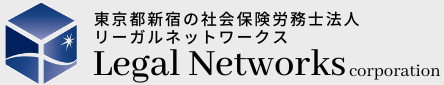所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |
|---|
受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/13~8/15) 年末年始(12/30~1/3)を除く |
|---|
公開日:2024/7/19
Vol.5 残業時間の基本

法的な基礎部分のおさらいと、勤怠管理の運用方法の参考にしてください。
この【社労士解説シリーズ】では、勤怠管理におけるノウハウや法的な考え方の整理等を全5回にわたりお届けします!
これまで、多くのお客様の勤怠管理システム導入を支援させて頂いた知見と、社労士としての法的知識から考えた”勤怠管理”についてご案内します。
1. 残業時間とは?
そもそも『残業』とは?辞書で引いてみると、”規定の時間のあとまで残って仕事をすること”と出ていました。
『残業』と聞いてどのような言葉やイメージが沸くでしょうか?少しあげてみましょう!
残業手当、割増賃金・・・、固定残業、定額残業・・・、早出残業、持ち帰り残業、サービズ残業、居残り残業、生活残業・・・
残業禁止Day(定時退社日)、残業申請許可制、残業命令、長時間労働、過労死、ブラック、忙しすぎ、スキル不足・・・
総じて、マイナスのイメージやお金に関する言葉が出てきますね。
【人事担当者として、残業をどのように捉えたら良いか?】
✓ 会社の費用(コスト)として!
✓ 従業員の評価・教育・スキルとして!
✓ 従業員の健康・会社イメージとして!
上記の視点から残業を捉えていくと、自社の課題や方向性、そして残業管理に関するフェーズが明確になっていくかもしれません。
残業時間の定義とは?
まずは、自社の『残業時間』が何を表しているのか?どのように定義された時間なのか?を整理しておきましょう!
例えば・・・
- 残業申請して、許可を受けた上で働いた時間である。
- 契約上の1日の時間を超えて働いた時間である。
- 終業時刻を超えて働いた時間である。
- 実働時間が法定労働時間を超えて働いた時間である。
・・・など、それぞれ定義が異なります。
残業時間の2つの意味
- 1労働契約上の残業時間
原則、雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載されている労働時間(所定労働時間)を超えて労働した時間を”残業時間”と言います。
会社は、従業員に働くことの対価として賃金を支払う契約関係にあります。これを雇用契約または労働契約などといいます。ちなみに、雇用契約は、民法上の規定に則った契約であり、労働契約は、労働契約法上の規定に則った契約です。
いずれも、同様の要件を満たす必要があるため、実務上では、あまり気にしなくても良いかもしれませんが、人事労務担当者のミニ知識として覚えておくと良いかもしれません。
さて話を戻すと、契約上の残業時間というのは、労使間の契約において、定義されることになります。つまり、契約上の時間を超えて勤務したときが、いわゆる、“残業時間”となるんですね。
契約上の時間を所定労働時間と言いますので、所定労働時間を超えて勤務した時間、つまり所定外労働時間が残業時間であると整理できます。

- 2労基法上の残業時間(法律用語では、時間外労働という)
労基法第32条(労働時間)で定められている1週間について40時間、1日について8時間(休憩時間を除く)を超えて労働した時間を”残業時間”(=時間外労働時間)と言います。
続いて、労基法上の残業時間とは、社労士解説シリーズの第2回でもご案内させて頂いた内容になりますが、労基法第32条(労働時間)の条文にて、規定された時間。いわゆる、1週間が40時間、1日が8時間の法定労働時間を超えて勤務した時間(法定外労働時間)を”残業時間”として整理しています。
ちなみに、法定上限を超えて勤務した時間を労基法上では、“時間外労働時間”と言うので、覚えておきましょう!
察しの良い方は、気が付いたかもしれませんが、36協定届のタイトルが、この“時間外労働・休日労働”に関する協定届となっています。つまり、36協定は、所定外労働時間に関する協定ではなく、法定外労働時間に関する協定を結んでいるのです。
一般呼称となっている、“残業時間”も、所定外労働時間と、法定外(時間外)労働時間のいずれを指している言葉なのか?
実務上では、各社、各雇用区分で異なった取扱いがなされていることが良くありますので、人事労務担当者して”残業時間“を捉えるときには、この2点を整理するとよくわかるようになると思います。
所定外労働時間と法定外労働時間(時間外労働時間)
続いては、所定外労働時間と法定外(時間外)労働時間との関係を整理します。
勤怠管理や給与計算を担当している方は、ここの整理も重要となりますので、改めて確認してみましょう。

この図の例では、始業時刻が、9:00で、12:00から13:00までが休憩、そして17:00が終業時刻という契約の方です。
この契約から、1日の所定労働時間が、7時間であることがわかります。そして、原則の労働時間制であれば、1日の法定労度時間は、8時間です。この従業員が、実際に9:00から働き始めて、23:00まで働いたと想定しましょう。
所定外労働時間が、残業時間であるとしている会社(いわゆる、法定上限を上回る労働条件設定をしている会社)は、
✔ 所定内労働時間が、7時間
✔ 所定外残業時間が、6時間
✔ 深夜労働時間が、1時間
となり、給与計算が実施でき、かつ、法定外(時間外)残業時間が5時間という管理をすることで、36協定の管理もできますね。
次に、法定内残業時間と法定外残業時間のそれぞれを残業時間としているい会社(いわゆる、法定上限通り賃金支払い条件としている会社)は、
✔ 所定内労働時間が、7時間
✔ 法定内残業時間が、1時間
✔ 法定外残業時間が、5時間
✔ 深夜労働時間が、1時間
となり、給与計算が実施でき、36協定上の時間も同時に管理することができるようになります。
このように、会社の労働条件において、所定労働時間と法定労働時間が同じなのか?所定労働時間が法定労働時間より短い場合は、残業手当の支払い条件が、法定どおりなのかそれとも法定を上回っているのかを整理することで、自社の残業時間を適切に把握することが可能になります。
残業時間の割増率とは?
雇用契約書や就業規則(賃金規程)および、労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)で定められています。
ここからは、残業手当を支払うときの割増率についても整理していきましょう。
時間外労働、休日労働、深夜労働に関しては、労基法第37条にて割増率が規定されています。
さらには、賃金については、契約上書面での明示事項となっているため、「労働契約書」や「就業規則、賃金規程等」で定められています。

こちらは、厚生労働省のモデル就業規則にある、割増賃金の支払い方を規定した条文例です。”残業に対する“となっておらず、”時間外労働“となっている点から、こちらは、法定労働時間を超えた場合の”残業時間“を規定していることがわかります。
法改正などで、自社の就業規則を変更するときに、モデル就業規則を参考にすることも多いと思いますが、言葉の定義をしっかりと理解していないと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあるので、注意が必要です。
特に、残業時間という言葉は、注意が必要な代表格です! 勤怠管理を見直すときにも大変役立ちますので、ここで今一度、押さえておきましょう!
割増賃金の種類と割増率とは?
法律上の割増賃金率も、今一度、押さえておきましょう。
自社との違いはないのか?また、あるならどの部分が有利な条件となっているか等を中心に再確認してみてください。

▶残業手当について
法定では“時間外労働”部分になります。
法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えた場合の割増率は、25%以上です。
次にまだ努力義務規定でありますが、時間外労働時間が限度時間を超えた時、60時間までの時間の割増率は25%以上。
そして、2023年4月から中小企業も含めて完全施行された時間外労働が60時間を超えた場合の割増率は、50%以上となりました。
▶ 休日勤務手当について
法定休日に勤務した場合になります。
法定休日に労働した時の割増率は、35%以上です。
なお、所定休日勤務した場合の法定割増率は有りませんが、週40時間時間を超える場合は、時間外勤務の割増率が適用されますので、覚えておきましょう。
▶ 深夜勤務手当について
深夜時間帯(22時~5時)に勤務した場合になります。
深夜時間帯に労働した時の割増率は、25%以上です。
これらは、すべて法律上の最低限度を定めているものになります。
これらを押さえた上で、会社の残業手当を支払うルールが契約上どのように設定しているのかを確認する必要があります。
割増率の具体例

法定の割増率をおさえたところで、ここからは時間外労働の割増率の具体例を見ていきます。
まずは、日単位での考え方になります。
▶ 時間外労働の割増率
(上の図参照)
【法定時間内残業】
17:00~18:00 1時間あたりの賃金×1.00×1時間
【法定時間外残業】
18:00~22:00 1時間あたりの賃金×1.25×4時間
【法定時間外残業+深夜】
22:00~5:00 1時間あたりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間
---★ポイント★---
法定時間外残業時間と深夜労働時間の割増率を125%25%と内数で捉えてると給与計算が簡単になります!!
【法定時間外残業】
18:00~5:00 1時間あたりの賃金×1.25×11時間
【深夜労働時間】
22:00~5:00 1時間あたりの賃金×0.25×7時間
★----------------★
▶ 法定休日労働の割増率
(上の図参照)
【法定休日労働】
9:00~22:00 1時間あたりの賃金×1.35×12時間
【法定休日労働+深夜】
22:00~24:00 1時間あたりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間
所定休日に労働した場合の割増率が、規定上どのようになっているかもぜひ確認してみてください。
次に、一週間単位での考え方です。

▶週次残業について
1週40時間を超えたら時間外手当を支払う必要があります。
(上の図参照)
【1日8時間、週5日勤務した場合】
1日8時間、週40時間を超えないので、時間外手当は不要です。
【1日7時間、週6時間勤務した場合】
1日8時間は超えませんが、週42時間労働となるため、2時間の時間外手当が必要です。
【1日7時間、週6日間勤務し、残業と早退がある場合】
火曜日は1日8時間を超えるので、1時間分の時間外手当が必要です。
また、水曜日に2時間早退しましたが、週の通算(火曜日の1時間分の時間外手当は除きます)で41時間労働となるため、土曜日1時間分の時間外手当も必要となります。
2.残業する時のルール
そもそも残業はしていいもの?
『 皆さんの会社では、業務上、“残業”が必要になったときの社内ルールは有りますか? 』
✔ 残業が必要になると、直接本人に残業をお願いしている。
✔ 終業時刻前までに、残業が必要な場合は本人から上司へ残業申請をしている。
✔ 基本的に残業するか、しないかは、社員本人の裁量に任せている。
※ 今は少ないかもしれませんが、残業した時だけ後から残業時間としてもらう会社もあるかもしれません。
いずれにしても、会社は残業時間の把握を何らかの形で実施しなければならず、事業の業態や会社の文化によって、
様々なルールが設定されていると思います。ここからは、残業をするときのルールについて、解説していきます。

そもそも、残業って法律上はどうなっているのでしょうか?
一般法である民法の面から考えると、契約内容として残業させることがあるのかないのかによって規定されます。
つまり、残業してもらうには、法律上の根拠として、契約上、残業させることができる旨の記載が必要になります。
あまり意識していないかもしれませんが、就業規則上にほぼ記載されており、昨今の労働契約書には残業の有無の記載がされていることがほとんどです。もし、この条文が入っていない場合は、会社から残業命令があっても応じる必要は契約上は無いとも言えるのです。
そして、特別法である労基法にて、この残業に制限がかけられています。最初の制限として、残業禁止(ここでは時間外労働および休日労働の禁止)となっています。 労基法第32条です。つまり、契約上、残業することがあるとしていても、労基法第32条で時間外労働が禁止されているということになります。法定上限以下の所定労働時間の場合は、法定労働時間までの残業は可能という事です。
しかし、皆さんよ~くご存知の36協定を締結することで、この第32条の規定はあるものの、時間外労働に対し労使合意が取れているなら、協定時間内であれば、残業(時間外労働)をしても、法的罰則は免除しますよ!という法律構成になっているのです。実務上での残業に対する感覚より、法律はかなり厳しく規定されていることに、今はまだギャップがあるかもしれません。ただし、これからの時代は、これらのギャップが少しずつ縮まる傾向がみられていることを押さえておきましょう。

つまり、残業を可能とするには、民法上の要件である労働条件において、残業の有無を規定し、かつ、労基法上の免罰効果をもたらす労使協定を締結することで、前提となる残業をさせることが可能ということになっています。
36協定は、有効期間が1年間で自動更新条項をおくことができませんので、毎年、締結する必要が出てきますので、くれぐれも注意が必要です。就業規則ならびに労使協定で、会社は従業員に対し残業して労務に服してもらる前提条件が整うことになります。
時間外労働は会社の命令が必要?
残業時の前提条件を整えた上で、次に必要になるのは、日々の残業の取扱いです。原則論でいうと、時間外労働は原則禁止ですから、協定における免罰効果を生む為にも、協定の内容を実行しなければなりません。
また、所定外残業であっても、就業規則等の根拠において、残業をさせなければならないので、いずれにしても、大体の場合、残業は、業務の必要性から事前の命令を持って、実施されるものとされています。
つまり、原則論では、会社からの残業命令ありきで、残業をするというのが建前です。
しかし、実務では、
✔ 社員本人の裁量で、その日残業するかどうか、またどの程度するかが判断されていたり、
✔ 残業するときは、事前に会社に申請をするルールがあるにも関わらず、事後に形式的に申請したり
と言った運用がなされているケースが今でも多くあるかもしれません。
上記のようなケースであっても、しっかりと適切な賃金が支払われ、労基法ならびに36協定上のルールが遵守されているのであれば、結果的に法的問題も発生せず、社員自ら自主的な勤務で成果も上がっているという理想形になるかもしれません。そうなるようにするには、労働法関連の知識を得る為の社員研修等を実施するのも良いのかもしれません。
そもそも、常に残業をしなければならないくらいの業務量であったり、社員自身の自主性に任せる訳にはいかないような場合等は、残業をさせるか、させないのか判断をきっちりと会社側がする必要が出てきます。こういったケースの場合は、残業してまで当該業務をする必要性等を上司が判断するフローを組み込む必要が出てきます。そうしないと、なし崩し的に法令違反となってしまい、事業運営上、法令遵守が重要なファクターの一つとなった昨今では、人事労務責任者としての職責を全うできていないということになりかねません!
36協定届でどのように記載されているか?
締結中の「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)」の内容を今一度確認してみましょう!
時間外労働をさせる必要のある具体的事由や業務の種類、労働者数、上限時間などが記載されています。
今後の残業時間管理の方法を見直していくのも良いかもしれません。

3. 時間外労働の上限規制とは?
2019年4月より働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。
時間外労働の上限規制は、まだ、皆さんの記憶にも新しいかと思いますが、働き方改革関連法案の一つの大きな目玉法案として施行されました。2024年からは、建設業や運輸業、医師など猶予期間とされていた事業もいよいよ適用されるようになりましたね。
ざっくりとおさらいすると、改正前も、労基法第32条、ならびに第36条はあって、法定労働時間を超える労働は原則禁止で、36協定締結をすることで免罰効果を得られるという内容ではありました。ただ、問題となったのは36協定締結時の最大時間というのが大臣告示という形で示されておらず、法律上の規制とはなっていなかったという点と、そもそも、36協定の締結ならび運用が不十分であった為、形骸化しているというものでした。
そこで、労基法第36条を改正して、時間外労働の上限規制を法律に明文化し、罰則を含めた形で、取り締まりを強化してきたというのが内容ですね。改正から、5年を迎え、行政の取り締まりも厳しさを増す中、会社も率先してコンプライアンス問題として積極的に取り組む姿勢もあり、しっかりとした管理が根付き始めているのを感じるところでもあります。

時間外労働の上限規制については、原則と例外、そして特例という3つのフェーズで管理が求められています。
▶原則 <法定労働時間>1週40時間以内、かつ1日8時間以内
▶例外 労使で36協定を締結→労基署へ提出→時間外労働に対する免罰効果
<36協定> 1ヶ月45時間以内、かつ年間360時間以内
▶特例 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等 ※年間6回まで!
時間外労働 年間720時間以内、かつ時間外労働+休日労働 1ヶ月100時間未満、
かつ2~6ヶ月までの平均で時間外労働+休日労働が1ヶ月80時間未満
つまり、時間外労働の管理というのは、賃金の適正な支払いとは別に、法令遵守をするための月毎ならびに年間での管理が会社に求められているのです。もし、この3つのフェーズを管理運用する仕組みが構築されていない場合は、労務責任者として、まずは、この仕組みづくりから取り組む必要があるかもしれません。
時間外労働の上限規制を守るための管理方法とは?
時間外労働の上限規制を守るための管理方法サンプルを見てみましょう。

まず、社内において、時間外労働の累積時間数の閾値を決めます。
この例では、時間外労働が35時間を超えるタイミングとしています。この時、自動でアラートが上がるような仕組みを用意すると良いでしょう。
次に、閾値を超えたら、該当従業員と該当従業員の上長とで面談をして、残りの稼働日と業務状況を確認します。
45時間以内で収まると判断した場合は、残りの稼働日の時間外労働状況を注視する形となります。また、このままだと45時間を超えそうであるけれども、超えないようするための指導を上長はするとよいでしょう。これは上長の権限で行うことができる部分です。 特に、時間外労働が多めになってしまう社員の傾向として、業務のプライオリティが判断できていないことが有りますので、しっかりと、判断して指導しましょう。
最後に、どうしても超えそうである場合は、特別条項の発動要件を確認したうえ、従業員代表へ協議もしくは通知をして、発動をします。
45時間を超えた場合は、年間の適用回数に累積していくという流れになります。
これらの管理を年間を通して実施していくとう流れになります。
こちらはあくまで一例ではありますが、これまで実施できていなかった場合は、中々の業務となることが予想されます。
まずは、しっかりとした仕組みを作り、現場の負担がなるべく抑えられる形での導入を志していただけると良いのではないかと思います。
法令を遵守するためのポイントとは?
月末になって確認してみたら、気づかぬうちに時間外労働の上限規制違反!!なんてことも起こり得ます。
✓ 日々の時間外労働の管理をきちんと行いましょう!
✓ 特別条項の適切な発動を検討しましょう!
✓ 年間を俯瞰した時間外労働の管理をしましょう!

リーガルネットワークスでは、貴社の目指す勤怠管理のフェーズに合わせて、最適なシステム運用のご提案とご支援をさせて頂いております。
無料相談会も開催しておりますのでお気軽にご相談ください!
詳しくは、リーガルネットワークス提供サービスをご確認ください。
お気軽にお問合せ・ご相談ください

| 電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
|---|
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
|---|
=免責事項=
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。
リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載している情報については自己責任のもとご活用ください。
無料個別相談実施中
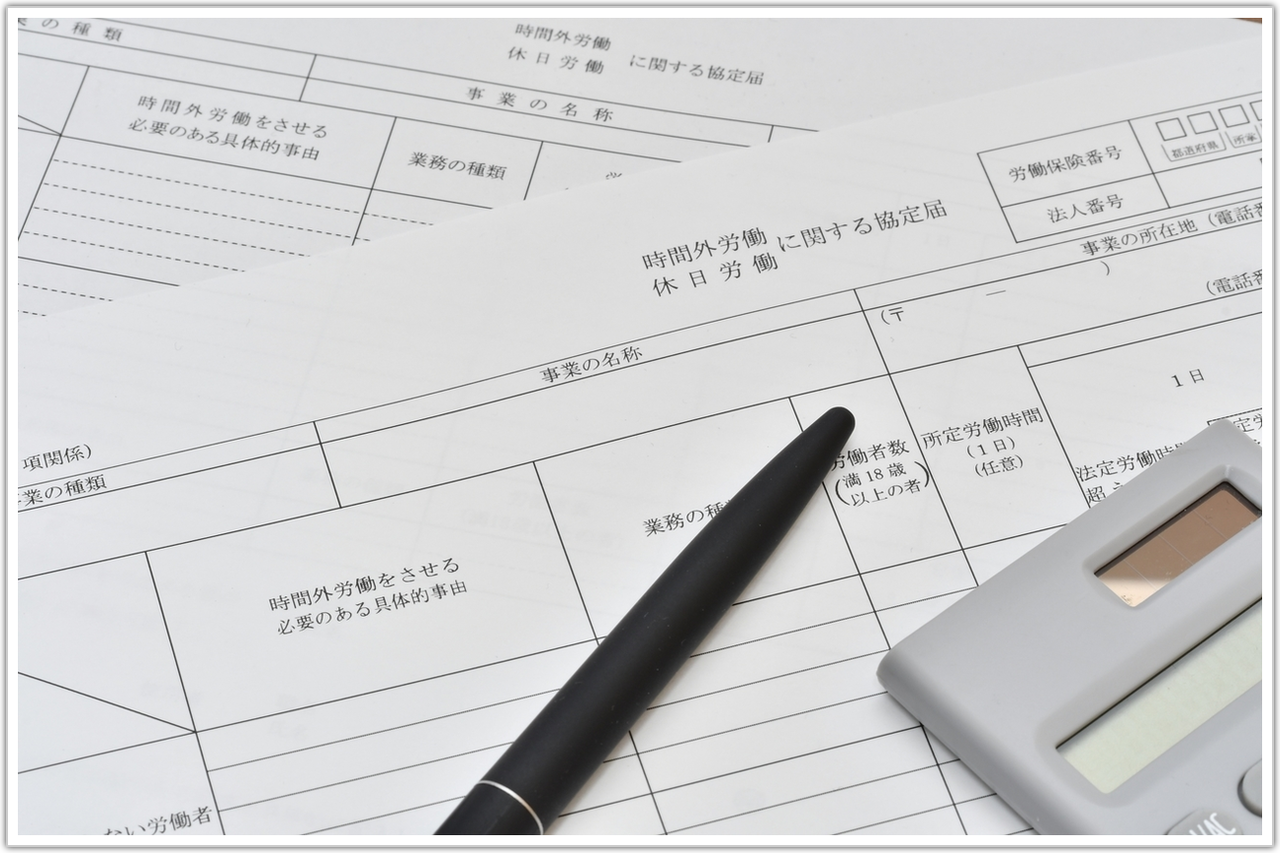
36協定なんでも相談会
年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。
免責事項
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。