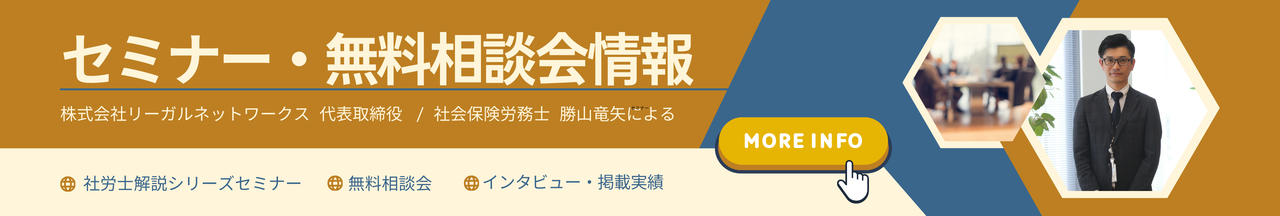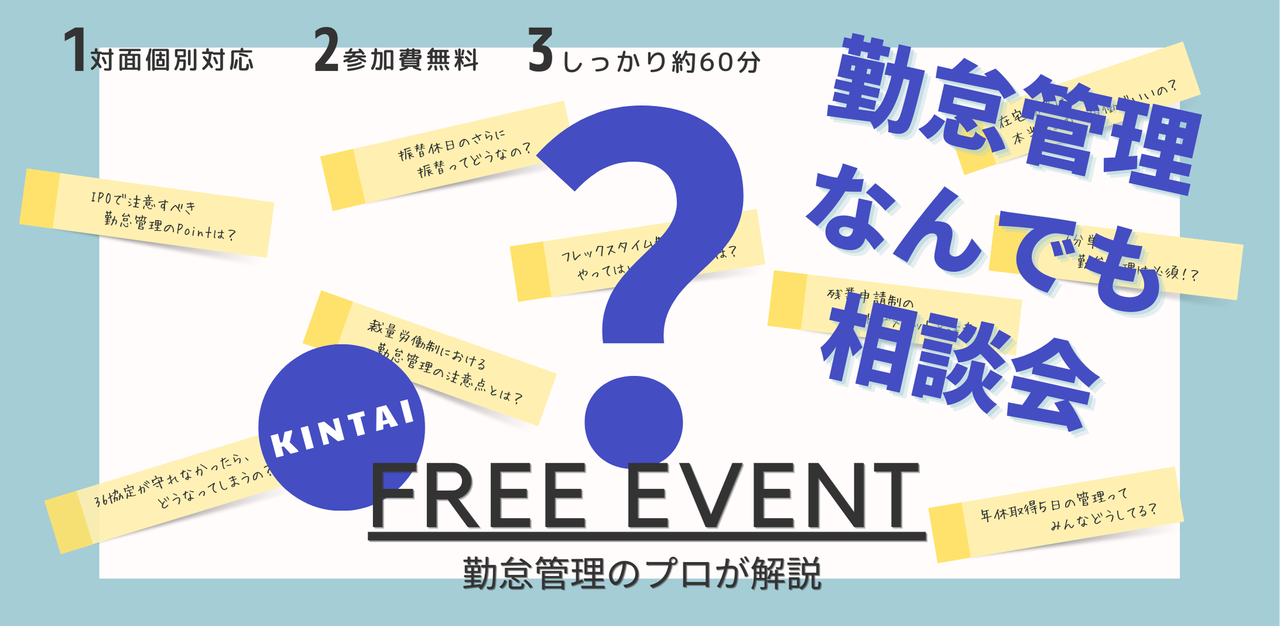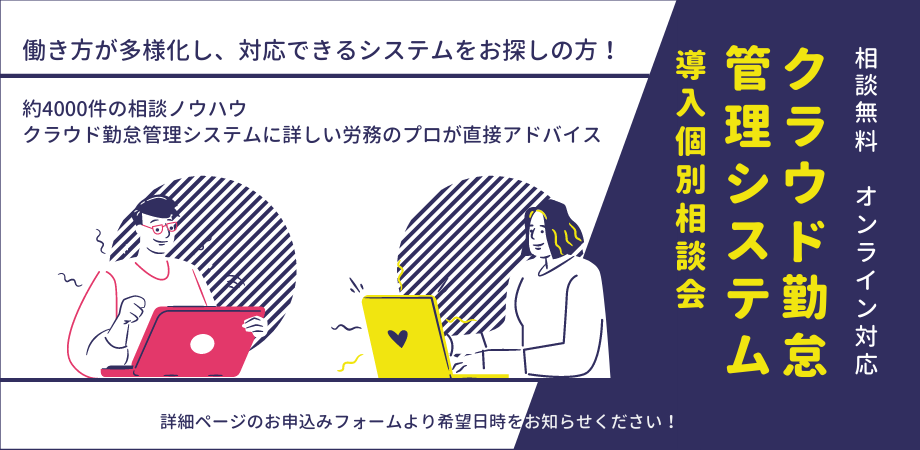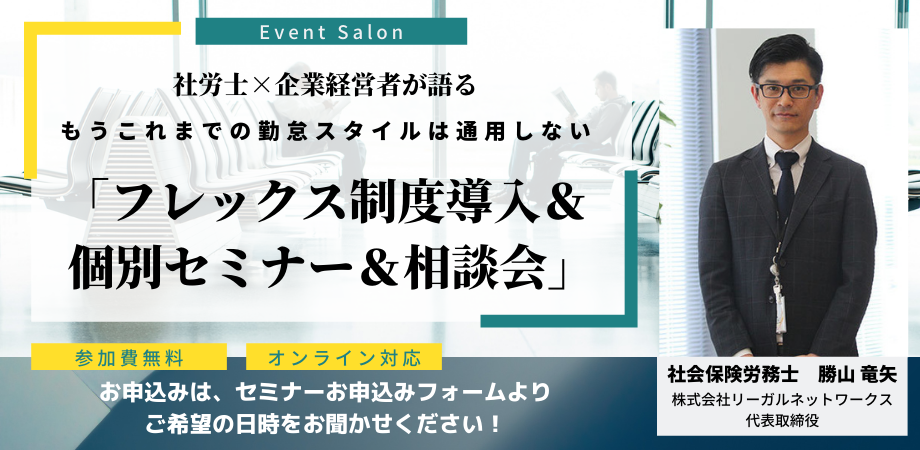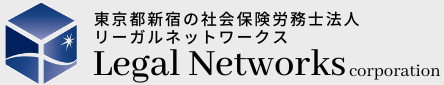所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |
|---|
受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/13~8/15) 年末年始(12/30~1/3)を除く |
|---|
公開日:2024/6/26
Vol.4 年休管理の基本

法的な基礎部分のおさらいと、勤怠管理の運用方法の参考にしてください。
この【社労士解説シリーズ】では、勤怠管理におけるノウハウや法的な考え方の整理等を全5回にわたりお届けします!
これまで、多くのお客様の勤怠管理システム導入を支援させて頂いた知見と、社労士としての法的知識から考えた”勤怠管理”についてご案内します。
1. 年次有給休暇とは?
従業員目線で言うと、働く上での権利として最もポピュラーなお休みかと思います。
ここ最近では、就職活動をする際の考慮条件に、”年次有給休暇の取得状況”なども入っているのではないでしょうか?
自分が働く会社を選択する時の一つの指標になってきているということですね。
一方、会社目線で考えると、現場を預かるマネージャーの方は、まだまだ業務の都合で自身のお休みが取れないというケースもあるようです。
しかし、経営者側も昨今は、従業員の福利厚生的な意味や、世の中から必要とされている会社の施策として年次有給休暇を重要な人事戦略のファクターとして捉えてきていて、法的な権利を超えるような運用を取っている会社も多いというのが年次有給休暇制度の特徴かもしれません。
今回は、法的に最低限整備されている年次有給休暇をおさえた上で、どのような上乗せ制度を取っているかを整理し、労務担当者として、今後の年次有給休暇の運用管理に活かして頂けれたらと思います。
【ここで質問です】年次有給休暇を、社内では何と呼んでいますか?
おそらく、一般的には”ゆうきゅう”と言う事が多いかもしれません。
前回(Vol.3 休日・休暇の基本)でお伝えしたとおり、休暇の中には、給料が発生する”有給”の休暇と、給料が発生しない”無給”の休暇があり、単純に”ゆうきゅう”と言ってしまうと誤解を招く場合もあるため、私たちは、年次有給休暇を”年休(ねんきゅう)”と表現しています。今回も”年休”と統一し、ご説明させて頂きます。
年休のはじまりは?!
年休は、国連の専門機関である国際労働機関(ILO)によって、1936年(昭和11年)に定められたとされています。
日本では、1947年(昭和22年)に定められた労働基準法にて法制化されています。
ちなみに、年休の起源は諸説あるものの、1910年頃にドイツの製薬会社が独自に有給休暇制度を設けていたようで、社員に14日間の有給休暇を与えて、勤続年数に応じた交通費まで補助し、旅先からハガキを送らせていたそうです。
ヨーロッパでは、産業革命以後、労働者から搾取するだけでは発展は望めないということに早くから気づき、反対に福利厚生を充実させることで社員の幸福度を上げて、会社への貢献度を高めてもらおうという試みを行っていたようです。
日本とヨーロッパ諸国との年休の違いとは?
時代背景も踏まえて、日本とヨーロッパ諸国との年休の違いを確認していきましょう!

▶欧州諸国
原則、年休は連続して取得するものという認識が強い。(1日単位で取得できる制度になっていない)
賃金前払い
心身の休養(バカンス)のため
▶日本
1日単位で取得するものという認識が強い。
賃金後払い
生活物資の獲得、病時の静養のため
このような違いが、結果として日本の年休取得率にも影響しているのかもしれません。
なぜ、日本が1日単位での取得、つまり分割取得を法的にみとめるようになったのか?
それは終戦後の焼け野原が広がる中、欧州のような心身の休養を目的として休暇を有効に利用するための施設も少なく、また労働者は生活物資獲得のため、週休1日以外に休日を要する状況にもありました。立案当時、労働者側使用者側双方の意見もあって、基礎日数についても分割を認めることになったそうです。
その後70年以上もの間、特例的に分割を認めたまま放置されているというのが年休の実態なのです。
日本の年休取得状況は?
では、日本の年休取得状況がどのような推移をたどっているのかを見てみましょう!
日本の年休取得状況を把握しておくと、競合他社と比べて自社の働きやすさのバロメーターになるかもしれません。

コロナ前20年くらいは、おおよそ50%を割るくらいの推移でした。あくまで、平均値ではあるものの付与日数の内、半分くらい取得できている程度でした。
これに対し、ヨーロッパ諸国では、ばらつきはあるものの年休の取得率は90%近い数値で推移しています!
働き方改革を実行していた2018年(平成30年)ごろに、政府は「取得率を2020年(令和2年)には70%にする!」という数値目標を立て、結果、56.3%という数値となり、目標未達成状態となってしまいました。
最新の『令和4年就労条件総合調査』では、
労働者一人平均付与日数は「17.6日」、そのうち平均取得日数は「10.3日」、平均取得率は「58.3%」となっています。
まだまだ、政府が掲げた目標には遠い状況であるものの、グラフから見てもわかるように取得率は上昇カーブを描いています。
労務担当者として、会社の年休取得状況が今後の有為人材の獲得に少なからず影響を及ぼす可能性がある点を考慮し、今後の対策を行っていくと良いのではないでしょうか?
年休の法改正の流れ

労働基準法施行時の年休は、先に説明した通り、戦後直後の混乱の中でスタートしています。
最初の付与日数は、6日でした。また、連続したものではなく、分割して取得ができる制度でした。
そして、年休制度の改正が入ったのは、約40年後の1988年(昭和63年)でした。
この時には、最低付与日数が6日から10日に引き上げられました。
さらには、計画的付与制度が創設されたりして、年休取得の方法に少し多様性がでてきました。
年休取得者に対する取扱いに関する判示も増え、不利益取扱いの禁止も条文化されています。

平成に入り、定期的に労基法改正がおこなわれ、その都度、年休制度の改正もなされています。
1994年(平成6年)には、初年度の継続勤務要件が1年から6ヶ月に短縮されました。
1999年(平成11年)には、2年6ヶ月を超える継続勤務期間1年後の付与日数が2日ずつ引き上げられました。
令和に入り、直近の法改正では、10日以上付与される労働者に対して、使用者(会社)が年に5日間を指定して取得させる義務(年5日時季指定義務)が導入されました。
これからの年休制度はどうなる?
ここは、だいぶ私見が含まれるので参考程度にお読みください。

これまでの年休は、取得する側次第(つまり従業員側)な発想があったかと思います。
「年休は取るか取らないかは本人次第で、取らなければ取らないで問題なし」
「年休取るなら、ちゃんと仕事に穴が開かないように配慮してね」
など、従業員自身が色々と配慮するのが当然!というような今までの発想だと、労働力人口が減少している今、従業員から選ばれる会社として残っていくのが難しくなるのではないでしょうか?
年5日時季指定義務の改正施行後5年を迎えようとしている今、労基署の監査では必ずと言っていいほど、年休の取得率はチェックされており、是正勧告を受けるニュースもチラホラ目にします。
年5日時季指定義務を果たすために、結果として、計画的付与制度を導入していく企業も増えていることから、年休の連続取得も普及するかもしれません。実際、働き方改革関連法施行にあたり、参考にした国はドイツやフランス等がベースとなっていると言われています。
さらには、2020年の民法改正による時効の5年化もあり、現在、特別法である労基法と民法との逆転現象も生じており、今後は時効(繰り越し)が3年ないし、5年となる可能性も捨てきれません。実際、賃金の時効は既に2年から3年となっています。
あくまで私見ですし、どうなるか分からないのですが・・・こういった背景も労務管理上の改善検討の際に参考にしていただけると良いかと思います。
労務担当者としての年休の捉え方
労務担当者として、年休をどのように捉えていく必要があるのか?を考えてみましょう!

- 1従業員のカテゴリごとに、年休取得状況を把握し、使用者(会社)側の年休に対するマインドを確認!
- 2自社の年休制度が、原則の法律最低限の運用がされているのか?優位な条件で運用がされているのか?を把握。
- 3最後に、年休取得率を一定数にする施策を検討し、人材戦略の一環として年休制度を捉えていく。

年次有給休暇は、働きやすい会社であるかどうかのバロメーターであり、
働きやすい会社=変化に対応できる会社(生き残る会社)に繋がるものであると捉えていただけると良いかもしれません。
2.年休の管理方法とは?
年休権が発生する従業員とは?
年休を付与する対象者について、原則を確認してみましょう!

以下の2点を満たせば、法的に年休が付与される従業員になります。
1つ目は、「雇入れの日から6ヶ月継続して雇われている」こと。
2つ目は、「全労働日の8割以上を出勤している」こと。
実務では、この原則以上の運用をしている会社があります!
例えば・・・
・入社と同時に付与する。
・入社月に応じて、案分して付与する。
など。
自社がどのような運用をしているかを把握し、そのメリット・デメリットを活かすと良いでしょう。
年休の(初回)付与タイミングとは?

▶労基法通り
原則、雇入れ日から6ヶ月経過日が最低条件となります。
法律最低限の運用をしていくという会社は、この方式となりますが、従業員は入社後6ヶ月間は年休がありません。
就職活動の際に、年休がいつから取得できるのか?という点が一つの選択要素になってくるかもしれません。
▶入社日方式
入社と同時に初回の年休付与日数を付与する条件となります。
法定を大きく上回る付与の仕方で、従業員からは魅力的に映ります。
しかし、入社後に縁なくすぐに退職することになった場合でも、付与された年休を利用できる状況となります。
▶案分方式
入社と同時に〇日付与し、6ヶ月後経過後日に残りの日数を付与する方式です。
上記2つの折衷案で、良いとこどりではありますが、管理上は若干工数が発生します。
年休の付与タイミング(2回目以降)とは?

▶労基法通り
初回の付与日を基準として、1年経過毎に付与する方式。
従業員数が増えてくると、バラバラの管理になるため、管理工数も増えていきます。
▶斉一付与方式(年1回)
年に1回、基準日を設定し、当該基準日に対象者に一斉に付与する方式。
基準日を会社で統一することで、年休の管理がわかりやすく、管理工数も低減する効果が見込めます。
従業員数が一定数を超えてくると、斉一付与方式を採用する企業も増える傾向にあります。
▶斉一付与方式(年2回)
年に2回の基準日を設定し、当該基準日に対象者に一斉に付与する方式。
2回目の付与までの期間が入社月に応じて異なることによる従業員間の不均衡を少なくするため、年2回の基準日を設ける方式を採用する企業もあります。
年休の取得単位とは?

年休の取得単位は次の通りです。
▶1日単位
法律上で定められているのは1労働日単位での取得が原則となります。
これは労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図り、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から規定されており、1労働日を分割して付与することは、本来予定されているものではありません。
▶半日単位
例外的に、労働者が希望し、使用者が同意した場合で1労働日単位の取得を阻害しない範囲内であれば、半日単位に分割して取得することも可能となります。
その場合、半日単位取得の取り扱いは、就業規則にて明確に規定しておく必要があります。
▶時間単位
労基法第39条第4項に記載されている通り、労使協定の締結を要することで、時間単位取得の取り扱いをすることができます。
時間単位での取得は、半休とは異なり年5日の範囲内など、法律上かなり制限を設けた上で導入が可能である点が半休と異なります。
年休の時季指定義務(年5日取得義務)とは?
年休に関する直近の法改正となります。2019年4月に年休取得率を向上させるために、使用者が時季を指定して計画的に年休を取得させることになりました。
使用者は労働者ごとに年休を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年休を取得させなければなりません。

▶年休の時季指定方法
使用者は、時季指定に当たっては労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
▶年休の時季指定を要しない場合
既に5日以上の年休を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、またすることもできません。
▶年休の時季指定のルール
使用者による年休の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません!
その他の年休ルールとは?
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、5年間(経過措置として当分の間は3年間)保存しなければなりません。
なお、必要な時にいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することを差し支えないとされています。
違反した場合の罰則とは?

上記のように、年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合は、30万以下の罰金などの罰則があります。
罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われます。

リーガルネットワークスでは、貴社の目指す勤怠管理のフェーズに合わせて、最適なシステム運用のご提案とご支援をさせて頂いております。
無料相談会も開催しておりますのでお気軽にご相談ください!
詳しくは、リーガルネットワークス提供サービスをご確認ください。
お気軽にお問合せ・ご相談ください

| 電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
|---|
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
|---|
=免責事項=
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。
リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載している情報については自己責任のもとご活用ください。
無料個別相談実施中
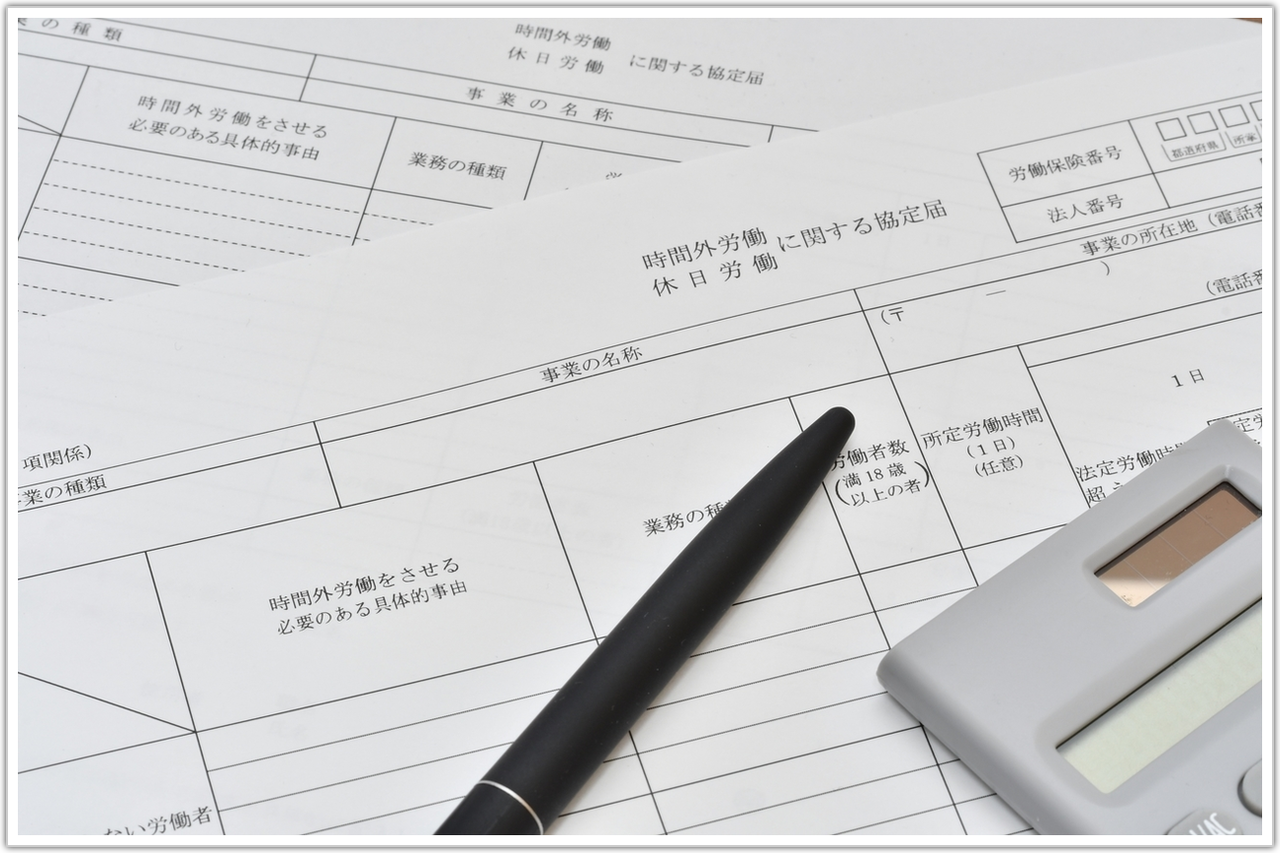
36協定なんでも相談会
年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。
免責事項
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。