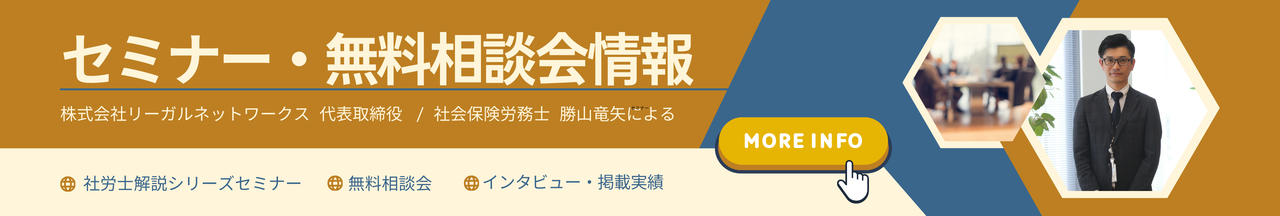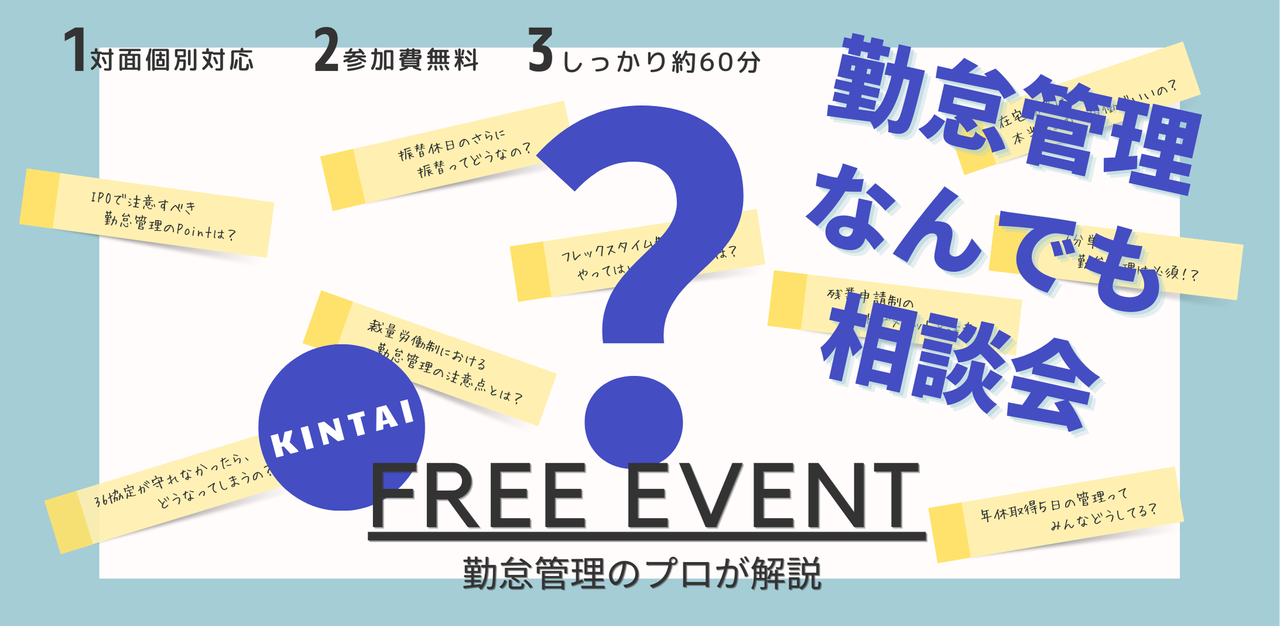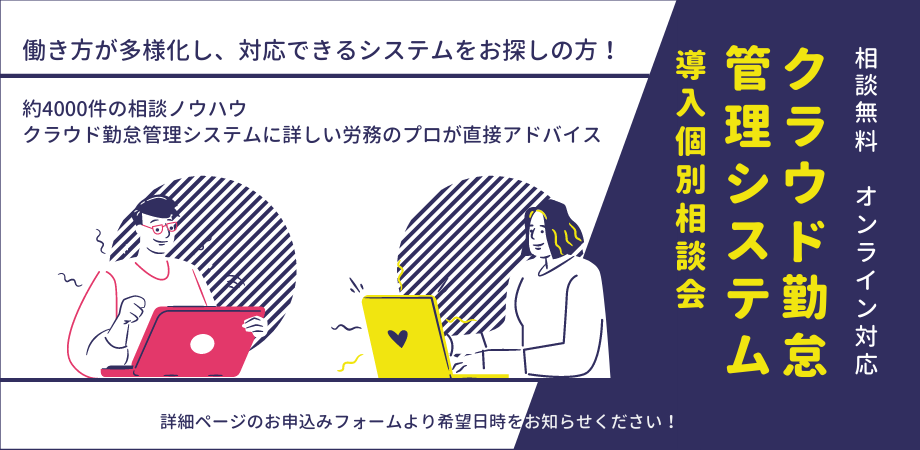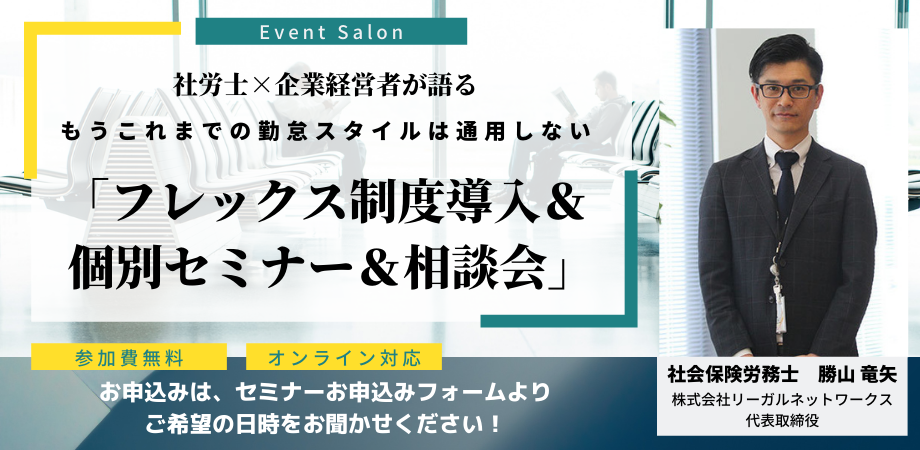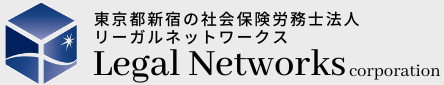所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |
|---|
受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/13~8/15) 年末年始(12/30~1/3)を除く |
|---|
公開日:2024/6/20
Vol.3 休日・休暇の基本

法的な基礎部分のおさらいと、勤怠管理の運用方法の参考にしてください。
この【社労士解説シリーズ】では、勤怠管理におけるノウハウや法的な考え方の整理等を全5回にわたりお届けします!
これまで、多くのお客様の勤怠管理システム導入を支援させて頂いた知見と、社労士としての法的知識から考えた”勤怠管理”についてご案内します。
1. そもそも”お休み”とは?
みなさんの会社には、どのような”お休み”がありますか?
「年次有給休暇があります!」
「うちは、土曜日、日曜日、祝日がお休みですね。」
労働契約上における”お休み”とは、何を指すのでしょうか?
労働契約上の体系と言葉の定義を整理することで、概要をつかむことができます。

▼暦日:こよみ上の1日のことです。
労働基準法では1日は定義されていません。
ですが、「1日は、午前0時から午後12までのいわゆる暦日という。」行政解釈が出されています。(昭和63年1月1号基発1号)
つまり、労働契約上、1日とは0時から24時までを原則的には指していると覚えておいてください。
この暦日において、労働契約上、次の二つに整理ができます。
・労働日:働く義務のある日。
・休日 :働く義務のない日。
そして、労働日において
・勤務日:実際に業務に就いた日。
・欠勤日:業務に就かなかった日。
・休暇日:働く義務のある日(労働日)にその義務が契約上、または法的に免除されている日。
”お休み”という一言でも、契約上の権利義務関係で取り扱いは大きく異なり、その後の給与計算などに影響を及ぼす可能性がありますので、注意が必要です。
休日の整理
既に解説した通り、労働契約上の労務提供義務の有無で、労働日と休日に区分されます。

▶労働日は、労働者が契約上、労務提供義務を負う日であり、通常、この日に勤務(労務提供)をすることで、賃金をもらう権利が発生することになる。さらに労働者は、労務提供義務と共に、職務専念義務や、企業秩序維持義務等も同時に負う日でもあります。
そして会社側は、労働日について、法定制限(いわゆる1日8時間等の制限)や”安全配慮義務”や”職場環境配慮義務”等も負うことになります!
▶休日は、労働者は契約上、労務提供義務が元々ない日となります。
ちなみに、契約上休日に業務することを労働条件として明記されていない限り、労働義務は発生しない日と言えます。
(参考)就業規則の条文に以下のような記載があるか?確認してみましょう!
『使用者は、労使協定の範囲内で労働者に時間外労働又は休日に労働させることができる。』
→この条文が入っていると、社員は休日に勤務を命じられた場合は、原則として断ることができないものと言えるのです!
なお、行政通達(昭23.4.5.基発55号)によると、休日とは、暦日を指し、午前0時から午後12時の休業であるとされています。
労働基準法によると・・・
| (休日) | |
| 第35条 | 使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 |
| 2 | 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
原則、休日というのは1週間に1回以上与えなければなりません。
例外条項として、第2項で4週間を通じて4日以上の休日を与えても法律上、良いことがわかります。(変形休日制)
ただし、2項については、行政通達で「第1項が原則であり、第2項は例外であることを強調し徹底させる」ことになっていることもからも分かる通り、実務で4週4日以上の変形休日制を利用する場合は、かなり厳しく制御が求められる可能性が高いと思われます。
休日の種類とは?

実務の世界では、休日がしっかり取れているような場合は、法定休日なのか、所定休日なのかあまり意識して注意する必要はないのですが、休日に働いてもらわなければならなくなった時に、法定休日なのか?所定休日なのか?に注意が必要になってきます。
▼法定休日とは
労働基準法で定める休日。
法定休日に働かせた場合、割増賃金率35%以上の支給が必要となります。
▼所定休日とは
企業が任意に定める休日。
週の時間外労働(週において40時間を超える)場合は、割増賃金率25%以上の支給が必要となります。
★所定休日については、就業規則等でその取扱いが規定されているのがほとんどですのでご確認ください!
なお、一般に、所定休日、法定休日の意識なく、休日出勤とか、休日労働と呼ぶことが多いと思いますが、労基法上の”休日労働”とは36(サブロク)協定に基づき、週1回又は4週4日の法定休日に労働させた場合を言います。
休日出勤した場合の割増賃金率のパターン
実務上、休日に勤務した場合のよくある割増賃金率のパターンは以下のようなものがあげられます。

① 割増率固定パターン
所定休日の割増率を法定休日の割増率である35%に合わせているパターンです。
このパターンのメリットは、休日出勤の割増率が一緒のため管理上の業務コストを抑える効果があります。
一方、デメリットとしては、休日出勤が多い会社の場合は人件費率が上がってしまう可能性があります。
② 割増率分類パターン
法定休日の割増率を35%と所定休日の割増率25%を分けているパターンです。
これは、週休2日制で、1日の所定労働時間が8時間の会社で比較的多く採用されています。
振替を同一週内で行い週次残業が発生しない状況であれば、①よりも人件費と管理上の業務コストも抑える効果があります。
ただ、祝日が休日の場合や1日の所定労働時間が8時間未満の場合は法律よりも高い割増賃金を支払っていることになります。
会社としてのデメリットと捉えられるかもしれませんが、労働者側からすれば、比較的納得性はあるパターンかと思います。
③ 割増率変動パターン
法律の最低限を設定するパターンです。
法定休日労働が35%で、所定休日労働は休日労働としてではなく、あくまで時間外労働としての割増率を設定するパターンです。
つまり、所定休日労働時間のなかでも、40時間を超えない限り、割増はなく、超えた場合のにみ25%支払います。
契約上、休日数が多い雇用形態の場合(一般的にはアルバイトやパートタイマーなど時給者)に多く採用されています。
デメリットとしては、管理上の業務コストが高くなることがあるので、休日出勤が多い場合はあまりおすすめできませんね。
いずれにしても、就業規則において、どのように定められているかによりますので、確認してみてください!
2.そもそも休暇とは?

労働義務のある日の中で、義務を果たした日、果たさなかった日、そして義務が免除された日に分類され、休暇は義務が免除された日になります。

労働義務のある日(労働日)に働かなかった場合の取り扱いは、欠勤日と休暇日に整理されます。
▶欠勤日
契約不履行状態。
働いていないため、賃金請求権はもちろん発生せず、その理由の如何によっては就業規則等での懲戒の対象となる場合もあります。
▶休暇日
労務提供義務を免除する権利行使状態。
労働日に休むことを予め権利として補償された日となり、懲戒の対象となることもありません。
休暇を取得することでなんらかの不利益を被るような取り扱いをしてしまうと、様々な労使トラブルに繋がるので注意が必要です。
ただし、事前に権利行使を表明する必要があるという点が実務でのポイントとなります!
なお、当該休暇が、”有給”の休暇であるのか?”無給”の休暇であるのか?により、賃金請求権の有無が異なります。
休暇の種類とは?

休暇は、法定休暇と所定休暇に分かることができます。
▶法定休暇
労働諸法令で、労働者に付与することが義務付けられている休暇のこと。
一番わかりやすい法定休暇は、”年次有給休暇”ですね。
その他にも、”裁判員休暇”や”育児休業”なども法定休暇になります。
▶所定休暇(または法定外休暇)
会社と従業員とが就業規則等の契約によって、付与された休暇のこと。
一般的には、”年末年始休暇”や”代替休暇(代償休暇)”などが採用されており、会社ごとに多岐にわたります。

休暇は、労務提供義務の免除効果がある上で、労働契約上、賃金を発生させるのか?賃金を発生させないのか?で整理されます。
▶有給の休暇
契約上、または、法令上、休暇取得時において賃金の支給を規定した休暇。
▶無給の休暇
契約上、休暇取得時において賃金支給は無しと規定した休暇。
おもしろ休暇制度(一例)
▶健康促進休暇 ・・・ 半年間欠勤しなかった社員に対して1日だけ好きに休みが取得できる制度
▶オセロ休暇 ・・・ 休日に挟まれた平日は休暇になるという制度
▶課題解決休暇 ・・・ 年3回まで誰かのための課題を解決するために使える有給の休暇制度
▶ライディングデー ・・・ 夏と冬に合わせて3日間の有給休暇が付与され、夏はサーフィン、冬はスノーボードを楽しめる制度
▶山ごもり休暇 ・・・ 役職者に対し1年間に1度必ず9日間の連続休暇を義務付けた制度。
(リフレッシュと共に、引き継ぎを発生させることで業務内容を改めさせるという目的も!)

リーガルネットワークスでは、貴社の目指す勤怠管理のフェーズに合わせて、最適なシステム運用のご提案とご支援をさせて頂いております。
無料相談会も開催しておりますのでお気軽にご相談ください!
詳しくは、リーガルネットワークス提供サービスをご確認ください。
お気軽にお問合せ・ご相談ください

| 電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
|---|
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
|---|
=免責事項=
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。
リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載している情報については自己責任のもとご活用ください。
無料個別相談実施中
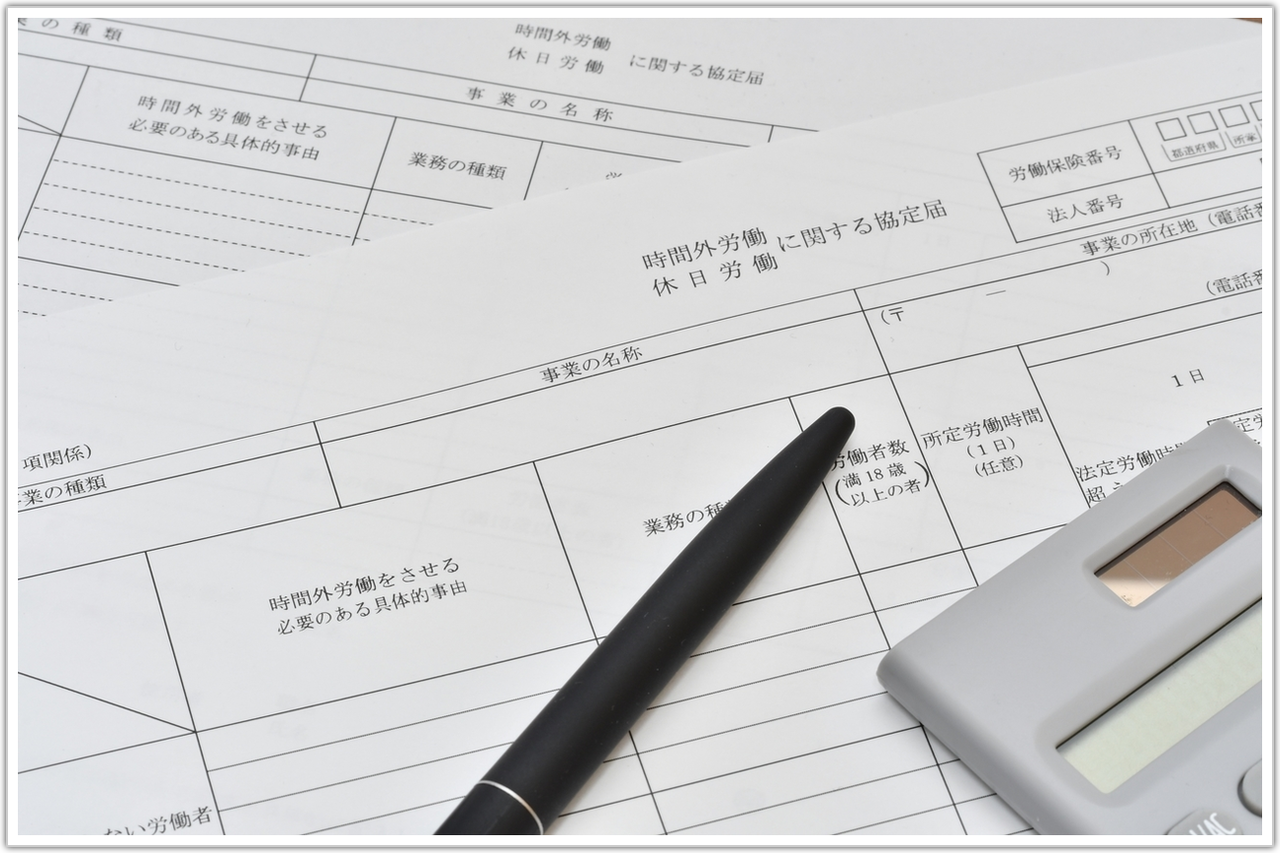
36協定なんでも相談会
年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。
免責事項
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。