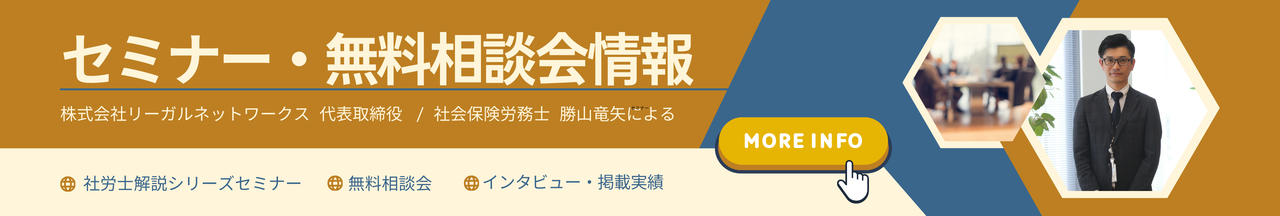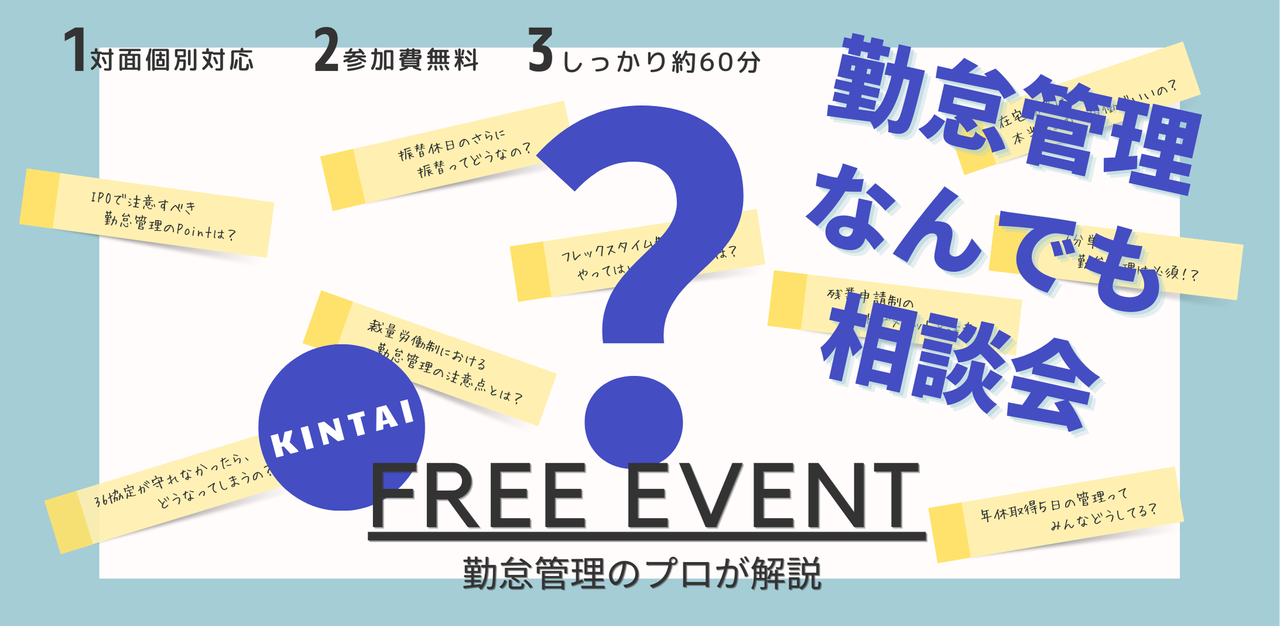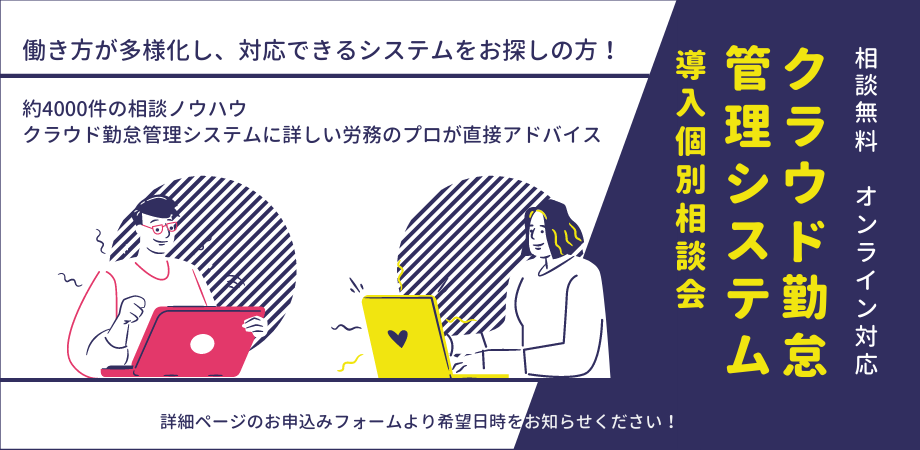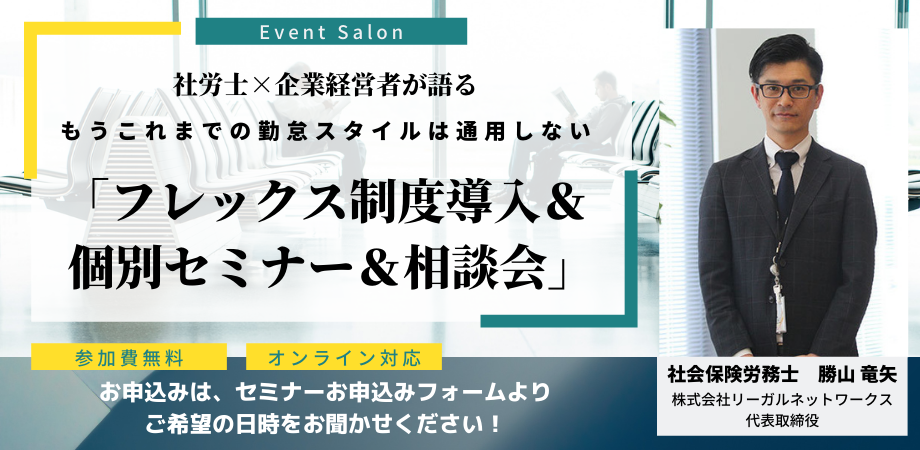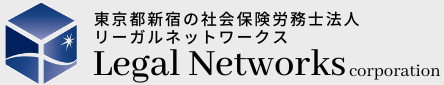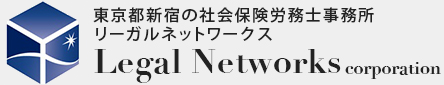所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |
|---|
受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/13~8/15) 年末年始(12/30~1/3)を除く |
|---|
勤怠管理システム選びのポイント
こんなお悩みはありませんか?

「勤怠管理システム」について
インターネットで検索したり、展示会などに行って資料を貰ってみたものの・・・
どのシステムがいいのか判断がつかない。
なぜ「勤怠管理システム」を導入する必要があるのか?

労働基準法により使用者は労働時間を適切に管理する義務を有しているのをご存知ですか?
勤怠管理システムは、出勤・退勤時刻を客観的に記録し、給与計算に必要な勤務時間や残業時間などの集計、欠勤や休暇を管理するものです。
使用者は労働時間を適切に管理する義務を有しているにも関わらず、一部の企業では、割増賃金の未払いや長時間労働といった問題が生じ、使用者が労働時間を適切に管理していない状況を改善すべく、政府による指導なども行われてきました。
働き方改革法における労働安全衛生法の改正に伴い、2019年4月1日より
「客観的方法による労働時間把握」が義務化されました。
法改正前の規定では、企業側からの指示あるいは従業員側の判断により就業時間の不正申告がなされ、残業代未払いや長時間労働による問題が発生したとしても、根拠が不十分なため解決せずトラブルになるケースも少なくありませんでした。
では、労働時間の把握をどのようにすればよいのか?
労働安全衛生法では、労働時間の把握について以下のように定めらえています。
事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。(労働安全衛生法 第六十六条の八の三)
この厚生労働省令で定める方法については、労働安全衛生規則に以下のように明記されています。
-法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等-
第五十二条の七の三 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
2 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。(労働安全衛生規則 第五十二の七の三)
なお、「労働時間の把握義務化」において、違反した場合の罰則規定はありません。
一方、今般の働き方改革の一環として労働基準法が改正され「時間外労働の上限」が法律に規定されました。これに違反した場合は、罰則を科せられるおそれがあります。

このように、労働時間を客観的方法で把握・管理する目的は、給与計算のためだけでなく従業員の健康管理の視点からも重要視されているのです。
このような理由からも、勤怠管理システムを導入するだけでなく適切に管理してく必要があるのです。
それでは、どのような勤怠管理システムを選べば、自社に合う管理ができるのか?約17年以上、勤怠管理システム導入相談を受けてきたノウハウを踏まえ、ご紹介させて頂きます。
勤怠管理システムの種類

勤怠管理システムは、大きくわけて以下の3種類になります。
タイムレコーダ型と集計ソフト
紙のタイムカードの代わりにタイムレコーダーを設置して単純な出退勤を記録します。タイムレコーダーの集計ソフトをPCにインストールし確認や修正をします。
- 客観的方法による労働時間把握ができる。
- タイムカードから労働時間を算出し、集計する作業が不要となる。
- 残業時間の算出間違いなど人為的ミスを防げる。
- 手入力されたExcelとタイムカードの相違確認作業が不要となる。
- 月末を過ぎないと把握できなかった残業時間の累計をタイムリーに確認できる。
など、労働時間計算の正当性が担保されつつ、集計作業が不要となることで業務効率が上がります。
時刻の客観的な記録のみが必要な場合は選択肢の一つとなるでしょう。
ただし、確認や修正作業が労務担当者に集中していまうため、従業員数が多い企業の場合は次に紹介するオンプレミス型(パッケージ製品)かクラウド型をお勧めします。従業員自身に気づきを与え、修正させていく事でさらに業務効率を上げることが可能となります。
オンプレミス型(パッケージ製品)
自社で保有するサーバーにソフトウェアをインストールし、勤怠管理システムを利用するものです。自社のネットワーク環境でシステム構築・管理するため初期費用が高くなりますが、セキュリティ面に強いことと、汎用的なシステムでは自社に合う機能がない場合などにカスタマイズが可能なものを選ぶことで対応ができるようになります。
近頃ではテレワーク導入を検討する企業も増えてきました。その際に、特定の環境以外からの打刻ができないと客観的な記録として残せない事や、テレワーク中の従業員を把握したい等の理由から、次のクラウド型へ切り替える企業もいらっしゃいます。
クラウド型
近年、もっとも一般的になっているのがクラウド型です。インターネットがつながる環境であれば、場所や時間を特定せずに利用することができます。
ハードウェアやソフトウェアの準備が不要で導入コストが安価なのも人気の理由です。
- 出張、外出、テレワークなど社外からの利用が可能になる。
- 打刻機が置けない環境でも打刻ができる。
- システムのインストール作業、バージョンアップ作業が不要となる。
- 法改正があってもスピーディーに対応できる。
- ワークフロー(申請承認の機能)により、紙での申請が不要となる。
- 年次有給休暇の管理簿作成が不要となる。
- アラート機能により、従業員自身にタイムリーに修正を促せる。
など、様々な機能を活用することができれば、さらに業務効率を上げていくことが可能となります。

導入したい勤怠管理システムの種類が決まったら、次は自社の管理に必要な機能を明確にします。
そこで、重要となるのが、自社の勤怠管理業務フローです!
自社の勤怠管理フローを書き出してみましょう!

箇条書きなど簡単なもので構いません。
まずは、書き出してみましょう!
(参考例)
<従業員の業務フロー>
・タイムカード他、日々の出勤・退勤の記録
・遅刻、早退、出張、直行、直帰、年休、休日出勤、振替休日などの申請
<上司の業務フロー>
・提出された申請書の確認・承認
・提出された出勤簿の確認・承認
<勤怠管理者のフロー>
・提出された承認済み申請書の処理(年休などの残日数管理)
・出勤簿の作成
・タイムカード、申請書類と出勤簿の付け合わせ
・集計時間、残業時間の算出
・従業員への修正依頼
・各種書類提出促進
・出勤簿の確定
・残業時間超過従業員のリスト化及び報告
・給与計算に必要なデータの作成
このように書き出した業務フローを元に、勤怠管理システムのどのような機能が必要か確認しましょう!
クラウド勤怠管理システム選定時に確認すべきこと

どの製品も機能や価格にさほど変わりがない場合、何を重要視しますか?
ここからは、クラウド勤怠管理システムを選ぶ際の確認ポイントについてご紹介していきます。
「クラウド勤怠管理」と検索すると65種類以上のシステムが見つかります。
全てのシステムを一つ一つ確認し、選定していくのは膨大な時間がかかります。さらにその中から自社に合うかどうかを検証し、判断していくのは大変な作業になります。
さて、ここで質問です!
勤怠管理システムを選定する際、あなたは以下の中で何を重要視しますか?
□ どのような会社が販売しているのか?(会社への信頼感)
□ いつから販売しているのか?(販売実績)
□ どのような企業が利用しているのか?(導入実績)
□ 製品の名前を聞いたことがあるか?(知名度)
□ 知り合いで利用している人がいるか?
□ どのような機能があるか?
□ 給与計算との連携がしやすいか?(必要なデータがとれるか?)
□ 従業員目線で使いやすいか?(画面が見やすいか?)
□ 導入費用や月額費用が適切か?
□ サポート体制はどうか?(質問対応・修正スピード)
□ 無料トライアルができるか?
□ 専門家に相談できるか?
まずは、重要視されているポイントで2~3製品をピックアップし、ホームページや資料、実際のデモンストレーションを見て確認していきましょう。
システム選定時の7つのチェックポイント
- 1
自社の業種・勤務形態に合うシステムかどうか
シフト制やフレックスタイム制、テレワークなど自社の勤務形態に対応できるか?
直行・直帰等、社内ルールに合う勤怠情報が取れるか?
- 2打刻方法が自社に適しているか
どのような打刻方法があるか確認。(ICカード、生体認証、PC・スマホ打刻など)
必要機器や設置場所の関係などは大丈夫か?
- 3従業員目線で操作しやすいか
従業員全員が簡単に操作できそうか?見やすい画面構成になっているか?
★ここが重要★
システムを選定していく中で、労務担当者は勤怠管理システムに慣れてしまいます。
ですが、会計システムなどとは異なり、勤怠管理システムは従業員全員が利用するものになります。
「分かりづらい!」と従業員からの不満がでないものを選ぶことをお勧めします!
- 4
導入前後のサポート体制はどうか
労務の専門家(社労士)との連携により、就業規則に合わせた設定方法など導入時に適切なアドバイスがもらえるか?
それとも、トラブル時の対応や基本的な操作方法に関するサポートのみの対応か?
- 5
給与システムとの連携はどうか
給与計算システムと自動連携できるか?もしくはCSVデータを簡単に出力することができるか?
- 6自社の特殊なルールに対応できるか
クラウド勤怠管理システムの場合、汎用的で標準的な仕様になっている事が多く、特殊なルールに適用しづらい場合があります。運用でカバーできる場合もありますが、システム導入するタイミングで規定やルールを見直される企業様もいらっしゃいます。
- 7価格はどうか
初期費用の価格は?打刻機が必要な場合の価格は?システムの月額利用料金は?など合計額を確認する。

最後に、絞り込んだ勤怠管理システムをトライアル登録をし、実際に操作しながら検証してみましょう!
弊社で推奨しているクラウド勤怠管理システム「AKASHI」の検証環境をご用意しています。
オリジナルの「AKASHI練習テキスト」を利用して、実際に操作しながら理解を深めて頂くことが可能です。
お気軽にお問合せ・ご相談ください

| 電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
|---|
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
|---|
=免責事項=
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。
リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載している情報については自己責任のもとご活用ください。
無料個別相談実施中
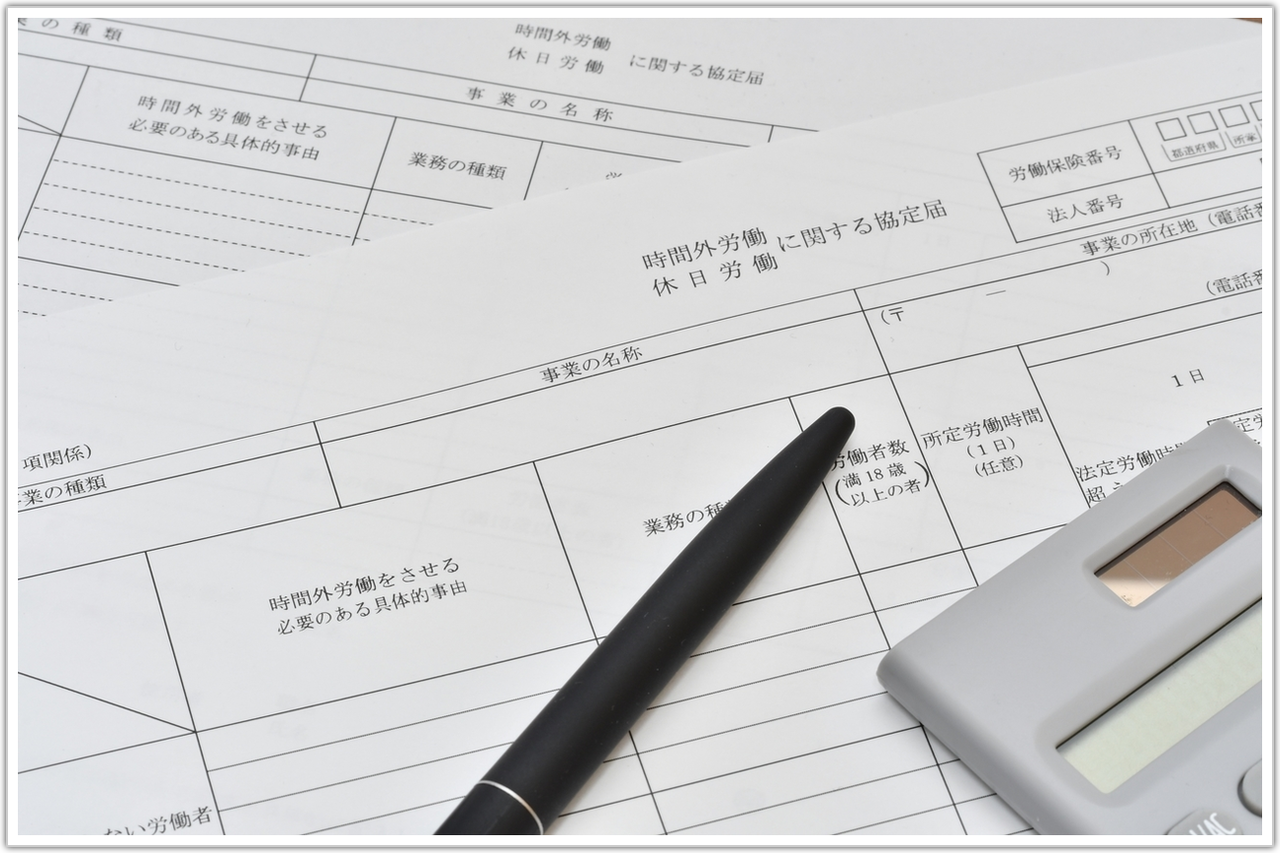
36協定なんでも相談会
年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。
免責事項
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。